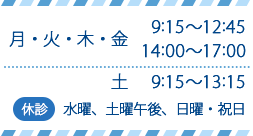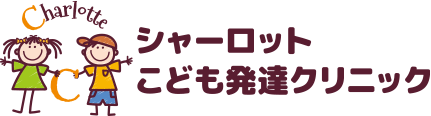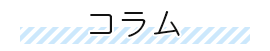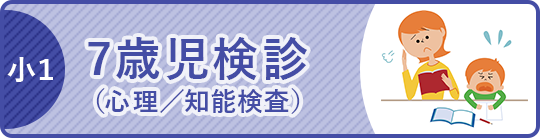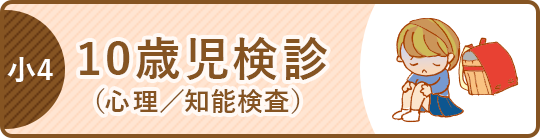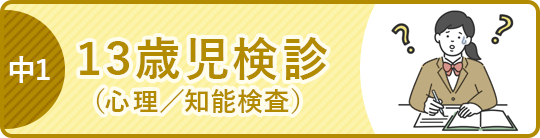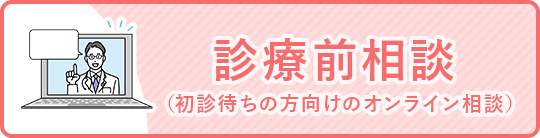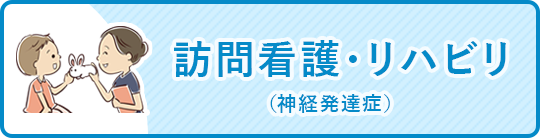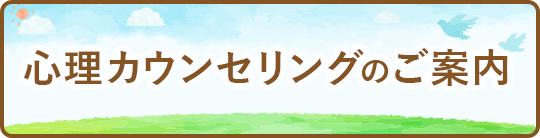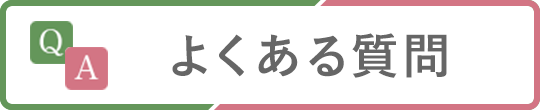ADHD(注意欠如・多動症)
ADHD(注意欠如・多動症または注意欠如・多動性障害)は、こどもの3~5%、大人の2%にみられるといわれており、学級や職場に少なくとも1人はその特徴を有する方がいます。
特に男性に多くみられ、幼いときほど症状が目立ちやすいのが特徴です。
そのため、幼少期は子育てしにくいことで悩まれて育児相談・受診につながるケースがしばしばです。
ADHDと診断するため以下の3つの特徴を確認していきます。
- 不注意:気が散りやすい、忘れっぽい、なくしてしまう、気づかない
- 多動性:じっとしていられない、しゃべりすぎる
- 衝動性:待てない
これらの症状が12歳未満からみられており、家庭だけでなく園・学校、職場においても症状がみられている場合にADHDの診断となります。
ただ注意しなければいけないのは、幼少期は発達的に多動であること、他の脳内の病気(例えば脳腫瘍、精神疾患など)でも同じ症状がみられることもあり、過剰診断・自己診断は禁物です。
こどもの発達や精神・神経疾患に精通している医師にきちんと診察を受け、医学的な評価を受けるのが支援の第一歩です。
ADHDの原因は、まだ解明されていませんが、脳内のドーパミンなどの神経伝達物質の関与、家族集積性(遺伝の関与)がみられることが報告されています。
そのため、決して育て方が悪いわけでも、こども本人の努力不足ということでもありません。
ADHDの治療
ADHDの治療は、以下の2本柱です。
①環境調整・自己理解の手助け
ADHDのこどもたちは自分で行動をコントロールすることがしばしば困難で、失敗体験がとても多くなります。
過剰な叱責による自己肯定感の低下を防ぐとともに、周囲の大人のメンタルヘルスについてもいっしょにケアしていくことがとても大切です。
また家庭以外の集団生活を行う上で、気が散らないような環境づくり、集中しやすい課題・時間設定の工夫が有効です。
またこども自身が達成感を得やすいようにポイント制やご褒美タイムの設定など取り入れていくことも良いでしょう。
また声掛けの仕方にも工夫が必要です。
「××してはダメ!」「どうして××できないの?」ではなく、「次は○○したらいいよね」とか「○○だとうれしいな」といった具体的な提案かつ前向きな声掛けがとても有効です。
これは、大脳辺縁系の影響が強く出やすいADHDのこどもたちの特徴のひとつで、否定的な声掛けや問いかけで極端に気分が落ち込んだり、逆に反発を招いたり、周りの人たちとの関係が悪くなることが多くなるためです。
これでは学習体験につながらないどころか、二次障害と呼ばれるこころの問題につながってしまいます。
とても単純なことですが、長い目でみると一番大切な介入方法ですので、ゆっくりと取り組んでみましょう。
どんなこどもでも新しいことを学ぶときには、ある程度間違いや失敗を経験しながら学習をしていくものです。
大きな失敗(事故や怪我を含む)を防ぎながら良い学習経験を積み重ね、お子さんのもつ良い面を一緒に育んでいきましょう。
また思春期以降になってくると自己理解が進んでいきます。
これまで周囲の大人が配慮してきた環境調整の仕方を自ら理解することができるようになります。
将来の自立した生活に向けて、自尊心が低下していないか、周囲との友人関係がうまくいっているか、インターネットやゲームなどに依存していないか、身の回りの清潔を保つことや適切な金銭管理の仕方、時間や期限を守ることなどの基本的な習慣を身につけられているか、など一緒に確認をしながら大人になる準備を進めていきましょう。
②薬物治療
6歳以上のお子さんでは、症状の強さに応じて薬の内服の提案をする場合があります。
代表的なADHDの薬は以下の4つです。
- コンサータ®錠
- ストラテラ®・アトモキセチン®(カプセル/錠/内用液)
- インチュニブ®錠
- ビバンセ®カプセル
なお、コンサータ®錠とビバンセ®カプセルは、不適切な使用による依存や乱用のリスクがあるため、2019年12月から患者登録制度が開始されました。
これにより、処方および調剤は事前に登録された医師および薬剤師のみ限られ、処方をうける患者さんもID番号が記載された患者カードの発行・所持が必要となっています。
いずれの薬剤も内服を開始した場合には主治医の指示通りに服薬し、からだの状態と症状をみながら服薬量を調整してもらうようにしましょう。